日本の伝統色は自然や動植物に由来した色名が多く、
例えば桃色や桜色、若葉色、山吹色などが挙げられます。
古代には赤・青・黒・白の4色しか表現がなかったものの、
時代とともに色彩表現は豊かになり、
「青」と「緑」の境界も細分化され、藍や蒼、碧など多様な呼び名が存在します。
こうした色名は単なる色の識別以上に、日本人の自然観や繊細な感性、
言葉による表現の好みを反映しています。
江戸小紋のように「地味な色の細分化で贅沢を楽しむ」文化も特徴的です。
海外と比べても日本の色彩文化は非常に詩的で深みがあり、
色辞典や伝統色のパレットを見る楽しみがあります。
こうした豊かな色彩感覚は日本の文化やデザインに独自の美をもたらしています。
![]()
500色の色鉛筆というのがありまして、普通に使うだけなら12色でじゅうぶんなのに、ずらっと並べると微妙な色合いが壮観です。 +1802
桃色とか桜色とか若葉色とか山吹色とか橙色とか植物が元になってる色がたくさんあるのが素敵だなって思う。 +490
日本の伝統色カラーパレットとか、動物や植物、空海山川まで色名に付いてるから見ていて楽しい。 +1071
色に名前がついてるのって素敵だよ。色の辞典をみてると、私たちは色と自然をよく結びつけていて楽しんでいるし尊んでいると感じる。 +710
前に「水色」が日本独特の言い方だと聞いて、このとても詩的な文化がこのまま続いてほしいと思いました。 +569
江戸小紋等『贅沢禁止?なら茶色等渋い色を細分化して細かい染めで地味に贅沢しちゃお。』の精神は西洋や中央アジアにはわかるめぇ。 +548
蜜柑色もあると思います。橙より黄味が強い。 +298
和色の図解で名前と色を見比べるの楽しいよね😊たまに、想像してた色との違いが分かって嬉しかったり😆 +273
緑と青を同じ「あお」と呼ぶかと思えば、青・藍・蒼・滄・碧と細かく分けてみたり、面白いなぁと思う。デザインに使うカラーチップでも、日本の伝統色とフランスの伝統色は見ているだけでも楽しい。 +300
海外は、色の違いは判っても呼び名が日本ほど細分化されていないだけだよね。青っぽい物はすべて「あお」、赤っぽい物はすべて「あか」って扱いか、青の#1、赤の#3・・・みたいな表現。色彩感覚というか、ちょっとした違いに全て名前を付けているのは日本特有だと思う。多分、日本人って言葉で表現するのが好きなんだと思う。 +480
昔の人は、紫・紅、朱・赤、橙・黄、青・藍を見分けてたし使い分けてた。緑は翠や碧と表され使い分けてた。黒・白に金銀や濃淡や明暗の表現もあり、極彩色豊かな感性が備わっていた。 +262
緑を青と呼ぶことについてですが、古代日本語には緑がなかったからだと言われています。古代日本語には色を表す語は、赤、青、黒、白の4つだけだったようです。この4つは後ろに「い」を足して形容詞にすることができます。その後の日本語の進化によって多くの色の表現ができるようになったのです。個人的には茜色や浅葱色といった日本語独特の表現が好きです。 +260
山は遠くなるほど青く見えます。近くの山は普通に緑でしょう。翠、碧、蒼などblueとGreenの間はたくさんあります。トンボ鉛筆の「色辞典」シリーズが好きです。名前の付け方もいい。 +76
「瓶のぞき」なんて色もある。どんな色か想像もできないだろうな。日本人の感性おそるべし。 +59
日本の色彩文化は非常に豊かで、
500色もの色鉛筆があるように細かな色の違いを楽しみます。
桃色や桜色、若葉色など植物に由来する色名や、
日本の伝統色は自然や動物、風景を反映していて詩的です。
古代日本語では赤・青・黒・白の4色だけでしたが、
時代とともに細分化され、緑も青と呼ばれてきました。
色の名前を細かく分ける感覚は日本独特で、
言葉で表現する文化が色彩感覚にも深く根付いています。
日本の色名は伝統や自然への敬意が感じられ、海外と比べても非常に繊細です。
(PR)資産運用するなら【DMM.com証券】!
![]()
![]()

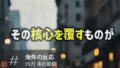
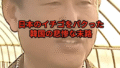
コメント